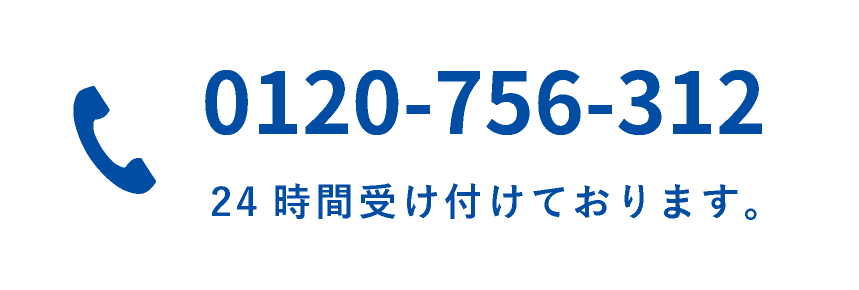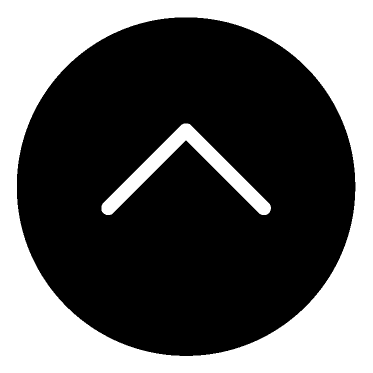福祉施設での防犯対策を進める社内研修にご協力させていただきました

今回、高齢者福祉施設の職員向け防犯研修に携わらせていただきました。
講師を務めさせて頂いたのは、出雲市内に施設がある高齢者福祉施設ひまわり園様の職員向け防犯研修会です。
今回の研修会は、基本的な事項をお伝えする座学形式に加えて、参加された職員の皆様と一緒に必要な対応方法を考えていくグループワーク形式での研修とさせていただきました。
福祉施設のBCP
この研修では、まず初めに、福祉施設における危機管理という面から、近年、様々な組織で取り組みが進んでいる BCP(Buisness Continuity Plan) についてご紹介しました。

このBCPについてはまだご存じない方もいらっしゃったため、最初にBCPの概念についてお伝えいたしました。
そして、具体的なイメージをいただけるように、平成28年10月に発生した鳥取県中部地震で被害を受けた倉吉市内の福祉施設の対応について、簡単にご紹介させていただきました。
ただし、大規模な地震災害について聞いても、「自分には関係ない」と思いがち。
そこで、出雲市における地震の発生確率をご紹介させていただきました。
あわせて、大規模な災害が発生した時に必要となる、事業再開までに行うべき対応についてお伝えしました。
高齢者福祉施設には常に見守りが必要となる入所者が多数いらっしゃいます。
そのため、高齢者福祉施設では、災害時における入所者の安全確保に加え、その後の生活環境の維持が重要であるため、防災対策に加えて事業継続のための備えが重要であることを確認いただきました。
夜間に施設内で不審者を発見したらどうするか?
続いて、今回の本題となる施設における防犯対策についてお伝えしました。
初めに、最近、福祉施設で発生している事件についてご紹介しました。
それらの事件を踏まえて、福祉施設の防犯対策として重要となるポイントやセコムが考える防犯対策のあり方、不審者が侵入した後の基本的な対応フローについてご紹介しました。
その後、グループワークを行いました。
各グループに、以下のような2つの状況を提示させていただきました。
【状況1】夜間に施設内で不審者を発見した
【状況2】職員に気がついた不審者が廊下の向こう側に逃げてしまった
それぞれの状況に出くわした時、職員の皆様はどのような対応を取るべきか?ということを検討いただき、ポストイットにどんどん書き込みをしていただきました。
その後、ポストイットに書き出されたやるべきことのリストを見ながら、
・現状のルールや設備でそれらができるか
・どのような順番で対応すべきか
・今後、どのような準備が必要か
ということについて、各グループで検討いただきました。

各グループで検討いただいた内容を発表いただいた上で、施設としてどのような対応が必要になるのか、ということについて全体で話を進めました。
最後に今回の内容を整理するとともに、セコムとしての考えについても触れさせて頂きました。
まとめ
今回の研修では、職員の皆様にBCPと防犯対策についてお伝えしました。
中心は防犯研修では弊社も初めてとなるグループワークによる不審者対応方法の検討でした。
上記のようなグループワークを通じて、今できること、そして、今後やるべきことを様々見出すことできました。
そして、私たちにとっても、新たな発見のある機会となりました。
1時間半の長い研修でしたが、職員の皆様はいずれも熱心にご参加いただき、本当にありがとうございました。